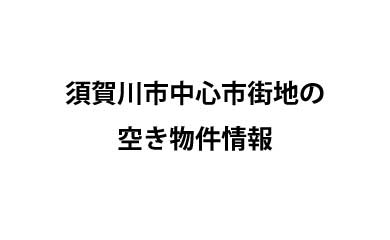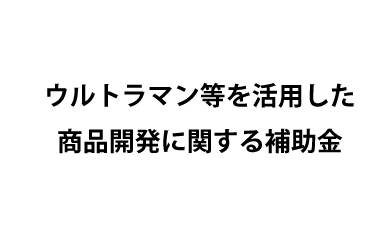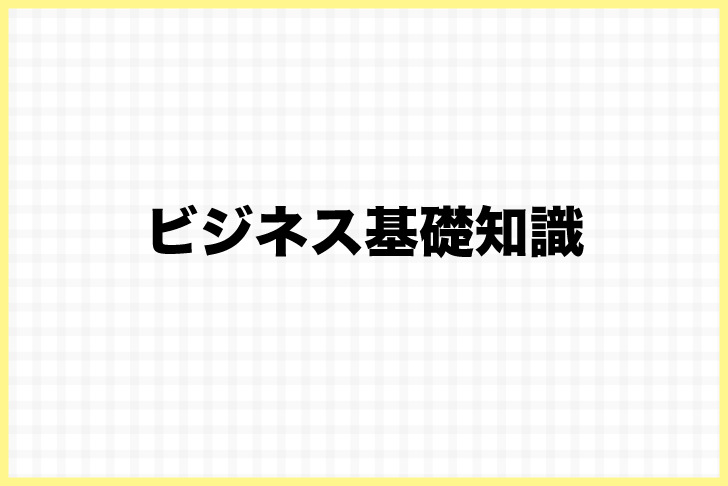創業初期“あるある”の落とし穴10と、実務で効く対策
創業直後は、アイデアの良し悪しよりも「資金が続く設計」「販路の確保」「法務・税務の先回り」で勝敗が決まります。日本政策金融公庫の最新調査では、開業費用の平均は985万円・中央値580万円、資金調達総額の平均は1,197万円で、うち金融機関からの借入が平均780万円(65.2%)、自己資金が平均293万円(24.5%)です。想像以上に現金が必要になります。そのため、事業計画書に基づき、確実に公的融資を活用し、余裕をもった資金繰りを行うという行動指針は非常に役立つと考えられます(日本政策金融公庫「2024年度 新規開業実態調査」)。
1. 収支が楽観的すぎる
創業者の多くが、売上予測を過大に見積もる一方で、開業後にかかる経費や予期せぬ緊急出費を過小評価しがちです。特に、売上入金と経費支払いのタイミングのズレ(キャッシュフローの悪化)を考慮しない設計は、利益が出ていても資金が底をつく「黒字倒産」に直結します。この落とし穴を避けるためには、売上を「最悪のケース」と「現実的なケース」の2パターンでシミュレーションし、最悪ケースでも事業が継続できるよう運転資金を確保しておくことが重要となるでしょう。
月次キャッシュフロー(入金・支払・残高・翌月予測)を更新し、最悪ケースでも3〜6か月回る運転資金を確保するといいでしょう。借入は使途(設備/運転)に応じて年限をあわせると有効です(公庫:新規開業・スタートアップ支援資金)。
2. 初期投資の過大化
サービスや店舗のクオリティを追求するあまり、「最初から完璧な状態」を目指して内装や高額な設備に多額の資金を投じてしまうケースが多く見られます。しかし、顧客の反応や需要が未検証の状態で固定費を膨らませると、事業の柔軟性が失われ、資金回収が困難になるリスクを高めます。この落とし穴を避けるためには、最小限の投資で事業をスタートさせ(MVP)、顧客の反応や売上実績を見ながら、必要に応じて段階的に投資を行うという考え方を徹底することが役立つと考えられます。
内装・機器・広告を“最初から完璧”にしないことが大切です。MVP(実用最小限の製品)で需要検証した後に段階的に投資を進めるといいでしょう。販路開拓費等は補助対象になり得るため、制度の趣旨と要件を事前に確認してください(中小企業庁:小規模事業者持続化補助金)。
3. 調達手段のミスマッチ
資金調達において、長期的に使用する設備(耐用年数が長い資産)への投資を、返済期間が短い短期の運転資金で賄ってしまうと、資金繰りがすぐに厳しくなります。資金の使途と融資の返済期間を整合させなければ、早い段階で元本返済に追われ、事業の継続に必要な手元現金を圧迫してしまいます。この落とし穴を避けるためには、資金使途を明確に分け、「設備資金は長期借入」、「運転資金は短期または回転資金」として、それぞれの計画に合わせた融資メニューを選択することが賢明でしょう。
短期資金で長期設備を賄わないようにするといいでしょう。据置期間や返済年限を事業計画にあわせることが有効です(日本政策金融公庫)。
4. キャッシュのズレ管理不足
売上は会計上計上されていても、実際にお金が振り込まれる入金サイトが長く(売掛金)、一方で仕入れや家賃、給与などの支払期日が早い(買掛金)ために、一時的に手元の現金が不足する状態を指します。このズレを適切に管理しないと、最悪の場合、支払いが滞り、信用問題に発展します。この落とし穴を避けるためには、契約時に可能な限り入金サイトを短縮し、支払いは期日分散を図るなど、現金の手元残高を常にプラスにする工夫が求められるでしょう。
入金サイトの短縮、前受・早期入金インセンティブの活用、在庫回転の設計、支払期日の分散で資金ショートを回避することがおすすめです。
5. 価格と粗利の設計が曖昧
「競合が安いから」という理由だけで安易に価格を決めてしまうと、自社の固定費(家賃、人件費、水道光熱費など)を賄うのに必要な粗利(売上総利益)が確保できません。必要粗利を無視した価格設定は、売れれば売れるほど体力が削られる「薄利多売の罠」に陥る原因となります。この落とし穴を避けるためには、まず自社が存続するために必要な固定費を計算し、そこから逆算して適正な価格設定を行うことが最優先の課題となるでしょう。
「必要粗利=固定費+人件費+税+将来投資」から逆算して価格設定をするといいでしょう。安易な値下げは致死的になり得るため、価値訴求と客単価向上策を先行させることが有効です。
6. 販路が一枚板
特定の紹介ルートや、Instagram、地域情報サイトなどたった一つの集客チャネルにのみ依存している状態は危険です。そのチャネルの仕様変更やトラブル、紹介元との関係悪化などが起こった途端、売上が急激に落ち込み、事業継続が困難になるリスクを抱えます。この落とし穴を避けるためには、集客チャネルを最低でも2〜3本確保し、一つのチャネルに頼らない「販路の複線化」を創業初期から計画的に行うことが、安定経営に繋がるでしょう。
紹介・1チャネル依存はリスクになります。ローカルSEO(Googleビジネスプロフィール)、予約・EC導線、SNS、地域イベント、商工団体連携など販路を複線化することがおすすめです。
7. 許認可・税務・インボイスを後回し
事業を開始する際に必要な行政への届出(開業届)、業種ごとに定められた許認可(例:飲食店の営業許可)、そして消費税のインボイス登録などの法的な義務を後回しにしてしまうことです。これが原因で、営業停止処分を受けたり、後の税務調査で追徴課税を受けたりする大きなリスクにつながります。この落とし穴を避けるためには、開業準備の初期段階で行政書士や税理士に相談し、必要な許認可と税務手続きのチェックリストを作成・実行することが不可欠な対策となるでしょう。
開業届の提出、業種別許認可、適格請求書(インボイス)の対応を前倒しで実施するといいでしょう(国税庁:開業届/国税庁:インボイス制度)。
8. 労務の未整備
初めて従業員(アルバイトを含む)を雇う際に、労働契約書の不備、残業時間に関する36協定の未締結・未届出、社会保険・労働保険の手続き漏れなどが起きる状態です。これらの労務管理の不備は、従業員とのトラブルや法令違反につながり、事業主として大きな責任を問われることになります。この落とし穴を避けるためには、従業員を雇用する前に、社会保険労務士などの専門家へ相談し、労働条件の明示や必要な届出を完璧に整えることが、安全な事業運営の土台となるでしょう。
従業員を雇うなら労働条件の明示、36協定の締結・届出など基本手続を遵守するといいでしょう(厚生労働省:36協定ガイド)。
9. 制度活用の情報不足
創業期に利用できる、返済負担の低い公的融資(日本政策金融公庫、自治体の制度融資)や、設備投資・販路開拓費用をまかなえる補助金(小規模事業者持続化補助金など)の情報を知らず、利用しないまま事業を始めてしまうことです。これらは資金繰りの大きな下支えとなるため、使わないのは機会損失となります。この落とし穴を避けるためには、地域の商工会議所や自治体が主催する創業相談窓口で、利用可能な最新の公的制度について定期的に情報収集し、事業計画に組み込むことが有効な戦略となるでしょう。
販路開拓・設備投資は国の補助金、公的融資は公庫や自治体の制度融資を確認するといいでしょう。地域では創業支援補助金等の枠も活用できます(例:福島県:創業等支援補助金)。
10. 孤立した意思決定
創業者が全ての経営判断を自分一人で行い、誰にも相談せずに進めてしまうことです。事業計画の客観的な評価、法務・税務に関する専門的な助言、資金繰りに関する外部のチェック機能がないため、誤った判断をしても気付くのが遅れ、致命的な失敗につながるリスクがあります。この落とし穴を避けるためには、市町村や商工団体が連携する「創業支援等事業」に積極的に参加し、外部の専門家や金融機関の客観的なアドバイスを定期的に受ける仕組みを持つことが大切だと考えられます。
市町村・商工団体・金融機関等が連携する「創業支援等事業」を窓口に、定例相談で外部目線を導入することがおすすめです(中小企業庁:創業支援等事業)。
まとめ
データ上、日本の起業後5年生存率は80.7%とされる一方、統計特性上“高めに算出の可能性”が指摘されています。楽観に流されず、手元資金・粗利・回転率・再来率を毎月点検し、国・県・市・公庫・銀行の制度を使い倒すことが、1年目を安全に走り切る近道です(中小企業白書2023)。
須賀川市での創業に関する相談・申請窓口
須賀川市 経済環境部 商工課 にぎわい創出係
〒962-8601 須賀川市八幡町135
TEL : 0248-88-9141